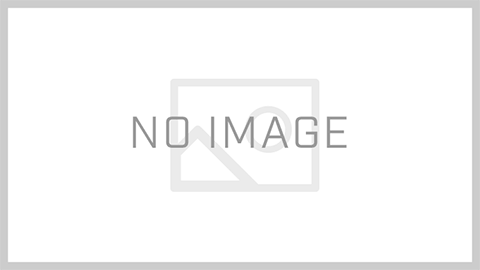父や愛犬が亡くなってしばらくは、その場にあるものを片付けることがとても躊躇われた。失ってしまった悲しみと同じくらいに、失ったことを確認していくひとつひとつの作業は刺さる。共有した時間は僕の細胞を形成していて、何処かにはあるはずなのに、時々見失ってしまったような息苦しさに襲われることがある。どんな風に一緒に散歩をしただろうとか、どんな風に名前を呼んでくれていただろうとか、思い出すカケラたちはどうしてこんなにも眩しいのだろう。
爪を切る 君のいた日の三日月の
ふあうすと2014年12月号「明鏡府」掲載